「なぜ日本は、ヨーロッパやアメリカの失敗から学ばずに“移民受け入れ”に傾いているのか?」
1. 人口減少・労働力不足が急激すぎる
-
日本は世界一の少子高齢化。
-
2025年以降、団塊世代が後期高齢者に入り、介護・医療・建設・物流などで深刻な人手不足。
-
企業や業界団体が「外国人労働者なしでは成り立たない」と政府に強く働きかけている。
👉 短期的な労働力確保が優先され、長期的なリスク管理は後回しにされている。
2. 政治の「先送り体質」
-
移民政策は国民的な議論を呼びやすく、政治家にとって選挙の票を失うリスクが大きい。
-
そのため「移民政策」という言葉を避け、技能実習制度・特定技能制度など「労働力確保策」として小出しに進めている。
-
本質的な「移民国家化」については国民に正直に説明せず、問題が顕在化するまで先送りしている。
3. 「日本は欧米と違う」という過信
-
政策担当者や一部の識者の間には、
「日本は島国だからコントロールできる」
「治安意識が高いから大丈夫」
といった**自国特有の安心感(例外意識)**がある。 -
しかし実際には、受け入れ人数が増えれば同じ問題が再現する可能性が高い。
4. 産業界の圧力と国際関係
-
建設・介護・農業・物流などは強い経済界ロビーを持ち、政府に受け入れを要望。
-
外交的にも、東南アジア・アフリカ諸国との関係強化の一環として「人材受け入れ」をパッケージで進めている。
-
結果的に「国益=移民受け入れが避けられない」というロジックが優先される。
5. 国民的議論が不足
-
日本では移民問題を正面から議論する機会が少なく、
マスコミも「人手不足」「外国人技能実習生の活躍」といったポジティブ面の報道が多い。 -
国民の多くはまだ「自分の生活に直結する大問題」として実感していない。
-
そのため、社会的な合意形成がないまま、実務的に制度が積み上げられている。
まとめ
日本がこの道を進む背景には、
-
急速な人口減少と人手不足(短期的ニーズの圧力)
-
政治の先送り体質(長期的リスクを正面から議論しない)
-
日本特有の安心感(例外意識)
-
経済界や外交関係からの圧力
-
国民的議論の不足
👉 要するに、「現場の人手不足」への即効薬として移民を入れざるを得ないが、「受け入れ後の共生リスク」を真剣に議論できていないのが日本の現状です。
移民問題(労働力不足)と経済問題は自民党政治の責任は大きくあると思います。
次回はその点を掘り下げてみたいと思います。
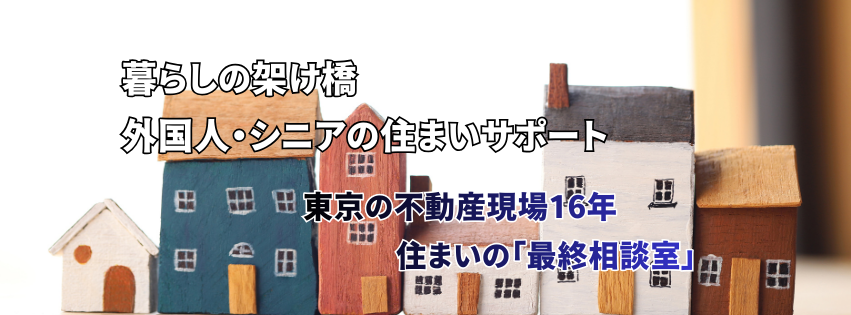


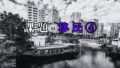
コメント