シニアの仕事「警備業務の給料」
日本における警備業務の給与の構造について説明いたします。
✅ 警備業務の構造(概略)
日本の警備員業務は、以下のような構造になっています:
- 発注者(依頼主)
例:建設会社、商業施設、イベント運営者など - 警備会社(元請け)
警備業法に基づき登録された事業者が、実際の業務を請け負う - 下請けや派遣登録会社(多重構造の場合あり)
一部では、再委託や孫請けなどもある - 現場の警備員(アルバイト・契約社員)
実際に誘導・監視を行う人たち
💰 発注額と実際の手取りの差
【例】交通誘導警備員の場合(東京都内基準)
| 内容 | 金額(概算) |
|---|---|
| 発注者が警備会社に支払う額 | 1人・1日あたり 18,000〜23,000円 |
| 警備会社が警備員に支払う日当 | 8,000〜10,000円前後 |
| 警備会社の取り分(管理費・利益) | 8,000〜13,000円前後 |
📌 なぜ手取りが安くなるのか?
- 中間マージンが高い
- 特に中小警備会社では30〜50%程度が「会社取り分」となることも
- 福利厚生・保険・教育研修費
- 警備業法に基づく教育(新任20時間、現任8時間/年)が必要
- 日払い・即金対応
- 日払い可能な警備会社は、流動性確保のために人件費を抑える傾向
- 現場の待遇が「未経験OK・高年齢可」である分、市場価値が低く設定されがち
📉 実際の時給感覚(都内・2025年現在)
- 日勤(8:00〜17:00):時給換算1,050円〜1,150円(休憩1hあり)
- 夜勤(20:00〜翌5:00):時給換算1,300円〜1,500円(深夜割増含む)
🧊 炎天下・悪天候などでも変わらない報酬
- 実際には酷暑・極寒でも基本日当は変わらないケースが多く、
- 最近は「熱中症対策費」や「夏季手当」として+500円〜1,000円出す企業も一部あり
💡参考:実際の警備会社の発注例
ある地方自治体が公表した契約書によると、
- 施設警備(駅前広場):年間契約2,000万円、警備員常駐2名体制
→ 1人1日あたり 約20,000〜22,000円程度
また、建設現場では、
- 交通誘導警備員:1人1日 18,000〜21,000円程度が一般的(首都圏)
📎 結論
発注額は1日2万円前後だが、警備員本人への支給額はその約半分
📢 今後の課題・動向
- 最低賃金の上昇(2025年は東京都で1,125円が目安)により、待遇改善の動きはある
- 人手不足により、「直雇用+高日当」型に切り替える動きも一部で見られる
- AIカメラやスマート警備ロボット導入による、人員削減の方向も進行中
この数値を見てどう思いますか?派遣会社の取り分と現場の取り分が同じ!
日本経済のおかしなところと思うのです、私は当然派遣会社の取り分はあって当たり前と思うのですが、1/3が妥当ではないでしょうか?
それが50/50で配分される現状なんです。
皆さんはどう考えますか?
【1】警備員全体の人数(全国)
-
約56万人(警備業法に基づく登録人数)
出典:警察庁「令和5年(2023年) 警備業の概況」
🧓【2】シニア世代の警備員人数
警察庁・総務省統計・業界団体のデータを総合すると…
年齢別構成(参考値・警察庁 2023年)
| 年齢層 | 割合(概算) | 人数(概算) |
|---|---|---|
| 60歳以上 | 約37〜40% | 約21〜22万人 |
| 65歳以上 | 約22〜25% | 約12〜14万人 |
「街選びは人生選び」
あなたの思い出の街、そしてこれから住むかもしれない街を動画で紹介中です。
ぜひ @cocosumutokyo でご覧ください。
ここ住むtokyo
【活動指針】 宅地建物取引士として16期、 生活保護受給者・外国人・留学生・難民の方など 住宅確保要配慮者へ1,000室以上の住まい提供に関わってきました。 日本で働く・学ぶ外国人が、 言語・文化・慣習の違いによって住まい探しで不利にならな...
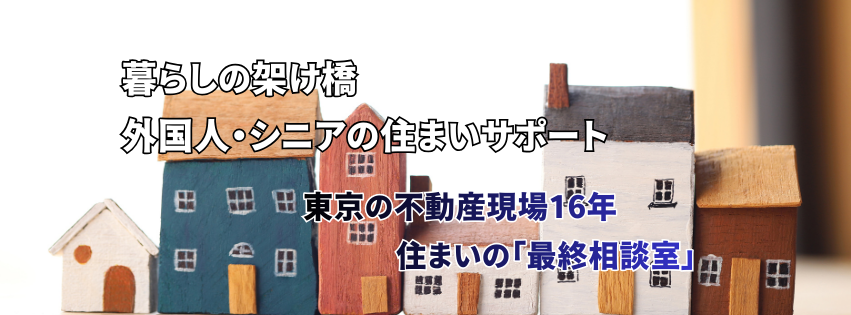
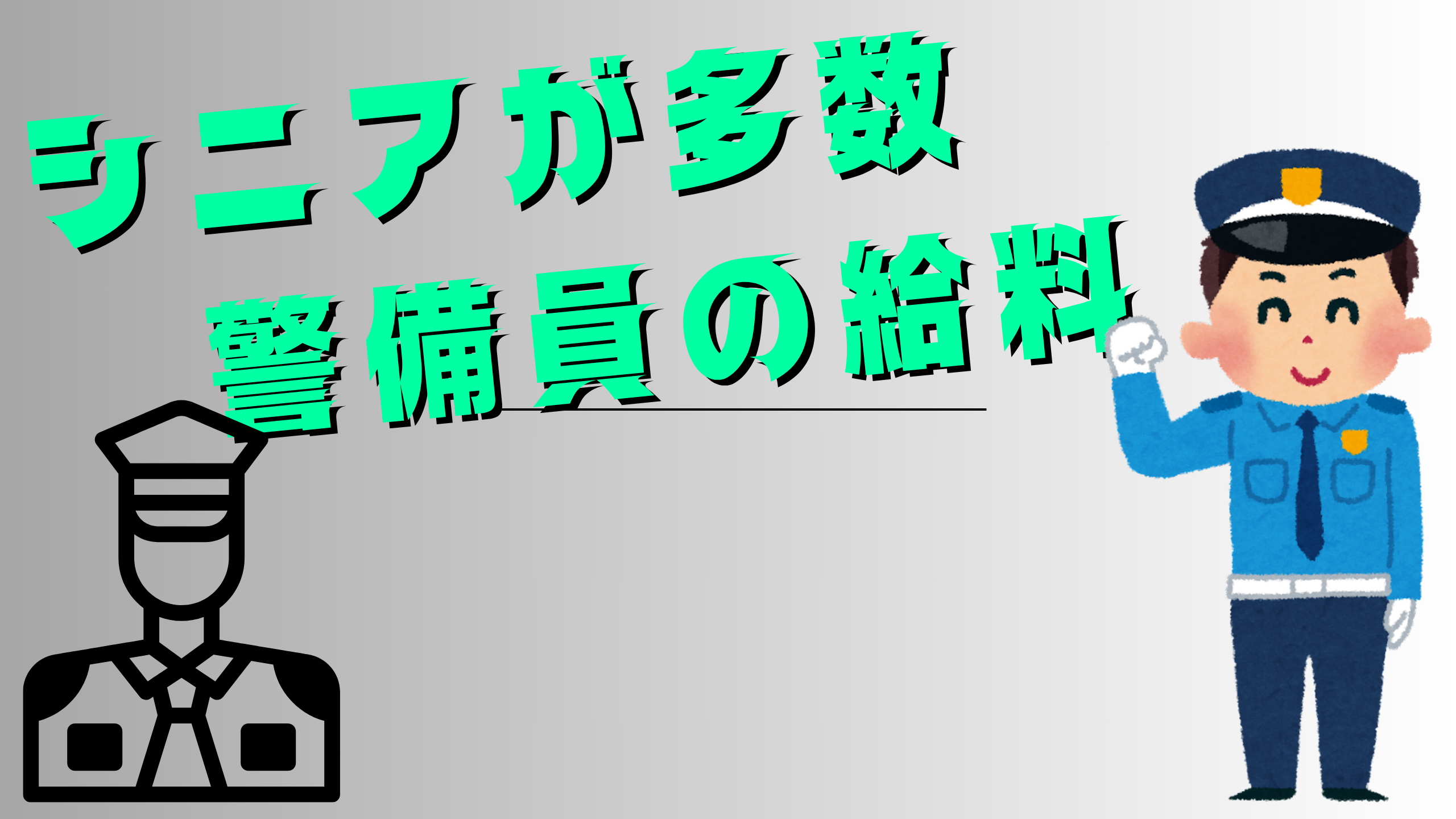

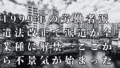
コメント