昭和40年代(1965〜1974年ごろ)の銭湯
日本の高度経済成長期の暮らしと深く結びついていました。まだ自宅に風呂がない家庭が多く、銭湯は日常生活の大切な場でした。
- YouTube
YouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。
昭和時代の銭湯は1950年代に全国約18,000軒あったといわれている。
昭和40年代の銭湯の特徴

① 外観・入口
- 唐破風(からはふ)の立派な屋根を持つ建物が多く、まるでお寺のような佇まい。
- 「ゆ」の暖簾(のれん)がかかっていて、夕方になると人々が暖簾をくぐって入っていきました。
② 脱衣所
- 広い板張りの床に木のロッカーや籐のかご。
- 天井にはプロペラ式の扇風機が回っていて、夏は汗をかきながら涼んでいました。
- マッサージ機や体重計もよく置かれていました。

③ 浴室
- 正面には大きな富士山のペンキ絵。これぞ銭湯の象徴。
- 浴槽は深めで、熱めのお湯(43〜45℃)。
- 白いタイル張りの床と壁で、少しヒヤッとする感触。
- カラン(蛇口)は座って使う低い位置にあり、木の桶でザバッと湯をかぶる。
④ 社会的な役割
- 近所の人たちの社交場。おじさんたちは世間話を、子供は湯船で遊んで怒られることも。
- 家風呂がまだ普及していなかったので、子供からお年寄りまで通う「生活の一部」。
⑤ 上がり場
- 瓶入りのコーヒー牛乳、フルーツ牛乳、サイダーなどが冷やされていて人気。
- 脱衣所の隅で将棋を指している常連客も。
つまり、昭和40年代の銭湯は「生活のインフラ」でありながら、「町内の交流の場」としても機能していました。
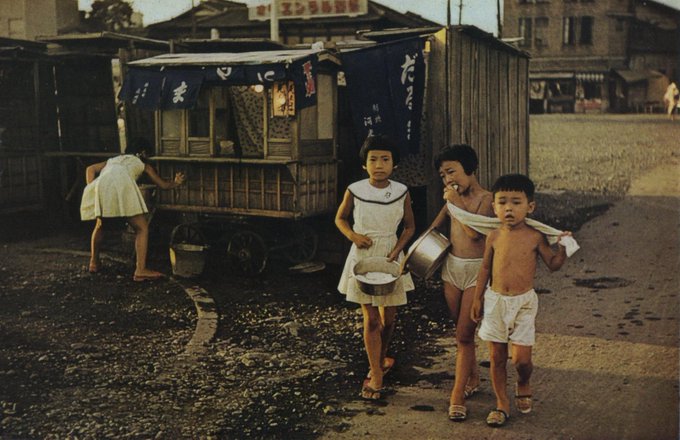
LINE公式アカウントはじめました。
初めての東京、誰に相談したらいいかわからない…。
治安や暮らしやすさなど本当に役立つ情報をお届けします。
ご相談もお気軽に。
LINE友だち登録はこちら👇



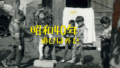
コメント